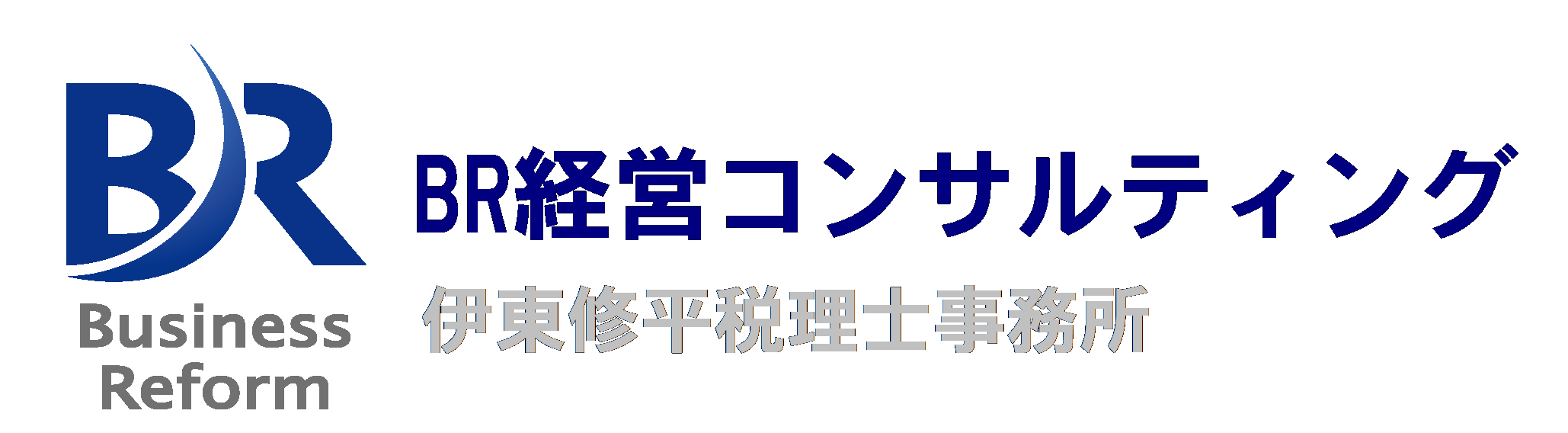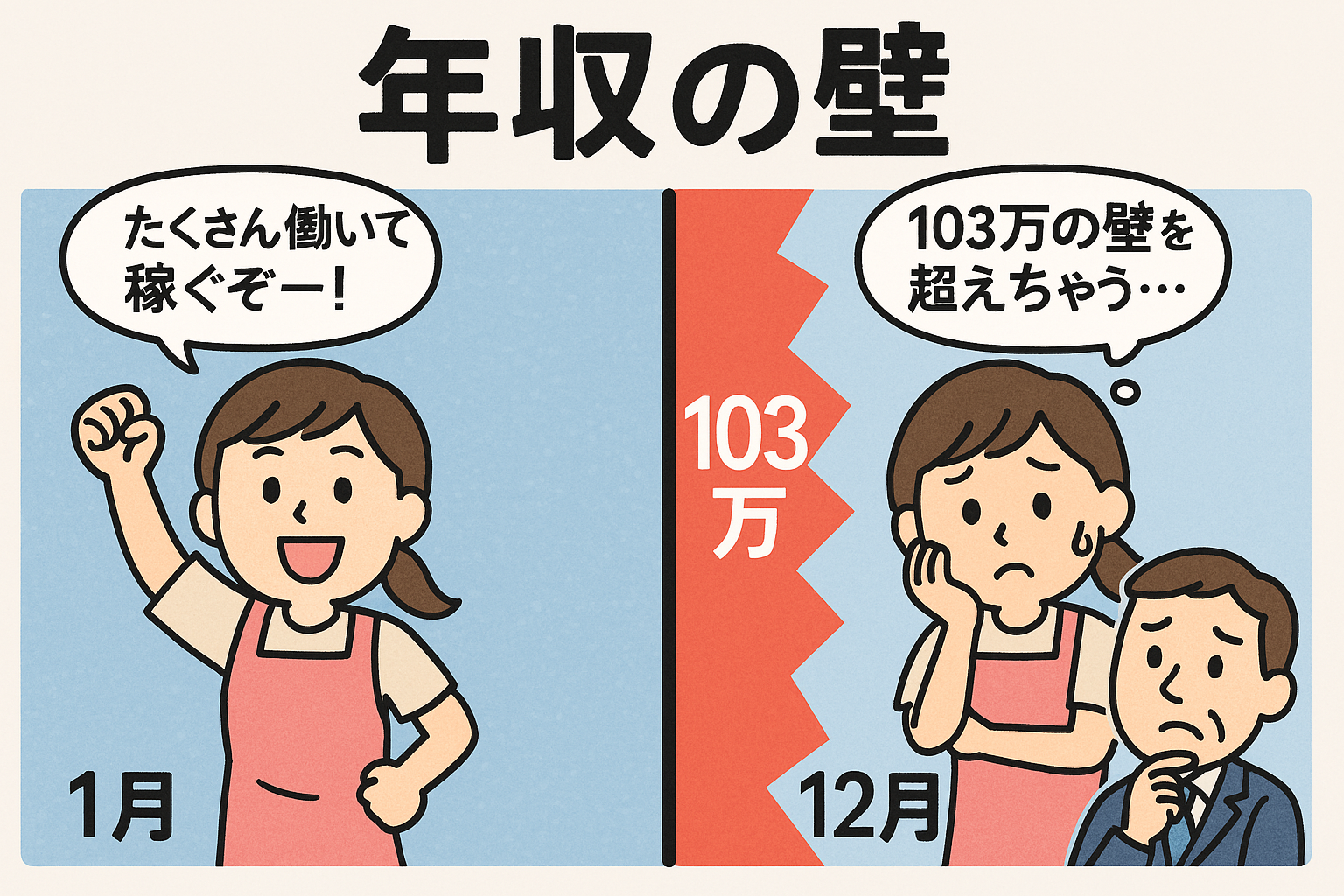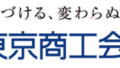「103万円の壁」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?パートやアルバイトとして働く人の年間給与収入が103万円を超えると所得税に影響するため、多くの人がこのラインを超えないよう働き方を調整してきました。
特に年末が近づくと「扶養内に収めるため今月はシフトを減らします…」という働き控えが起こりがちで、忙しい時期に企業は人手不足に悩む一因となっていました。
こうした状況を改善すべく、令和7年度(2025年)の税制改正では「年収の壁」見直しが行われ、大きな変更が加わります。本記事では、その主なポイントと中小企業の経営現場への影響、対応のヒントを解説します。
103万の壁
従来、基礎控除48万円+給与所得控除55万円=103万円を超えてパート等により収入を得ると、所得税の課税が発生していました。
令和7年度改正で、以下の通り、基礎控除・給与所得控除の引き上げが行われます。
基礎控除の改正(所得税)
1.原則:基礎控除は48万円から58万円に引き上げる(恒久的措置)
2.基礎控除の特例の創設
特例①:低所得者層の基礎控除額を95万円(+37万円)とする(恒久的措置)
特例②:中間所得者層の基礎控除を最大30万円上乗せる(時限措置:令和7・8年限定)
| 給与収入 | 所得金額 | 令和6年まで | 令和7年 | 令和8年 | 令和9年以後 |
|---|---|---|---|---|---|
| ~200万円 | ~132万円 | 48万円 | 95万円 | ||
| ~475万円 | ~336万円 | 88万円 | 88万円 | 58万円 | |
| ~665万円 | ~489万円 | 68万円 | 68万円 | ||
| ~850万円 | ~655万円 | 63万円 | 63万円 | ||
| ~2545万円 | ~2350万円 | 58万円 | 58万円 | ||
| ~2595万円 | ~2400万円 | 48万円 | |||
| ~2645万円 | ~2450万円 | 32万円 | |||
| ~2695万円 | ~2500万円 | 16万円 | |||
| 2695万円~ | 2500万円~ | 0万円 | |||
※所得2450万円以上になると段階的に基礎控除が減っていくのは従来通り
※住民税の基礎控除は従来通り、43万円。(改正なし)
給与所得控除の改正(所得税・住民税共通)
年収190万円以下の場合、給与所得控除額が55万→65万円に増額されました。
| 給与収入 | ~令和6年(改正前) | 令和7年~(改正後) |
|---|---|---|
| ~162.5万円 | 55万円 | 65万円 |
| ~180万円 | 給与収入×40%-10万円 | |
| ~190万円 | 給与収入×30%+8万円 | |
| ~360万円 | 給与収入×30%+8万円 | |
| ~660万円 | 給与収入×20%+44万円 | |
| ~850万円 | 給与収入×10%+110万円 | |
| 850万円~ | 195万円 | |
実務的には
中小企業の経営者にとっては、従業員から「今年からはもう少し働いても大丈夫なんですよね?」と相談を受けるケースも出てくるでしょう。
本改正は、令和7年1月~支給する給与で適用となります。
なお、令和7年度については、給与計算時にいくら源泉徴収するかを決める「源泉徴収税額表」は更新されないこととなっています。従来と同じ計算方法により所得税を給与から源泉徴収した上で、年末調整時に新しい控除を適用して再計算・調整することとなります。
特定親族特別控除の導入:大学生アルバイトの「扶養外れ」対策
扶養控除・特定親族特別控除
2025年の税制改正でもう一つ注目なのが、新設される「特定親族特別控除」です。
これは主に大学生くらいの年齢(19歳以上23歳未満)の扶養親族がいる家庭向けの措置で、親の扶養する子どもがアルバイト等で103万円を超えて稼いでも、一定の範囲内で親の税負担が増えないようにするための新しい控除制度です。
従来は、19~23歳の子供を扶養親族としている場合に、扶養する親に63万円の控除がありました。しかし、子どもが少し多めにアルバイトをして年収103万円を超えてしまうと、いきなり控除がゼロになってしまい税負担が大きくなることから、大学生の働き控えが起きていました。
今回の改正で、19~23歳の扶養親族の年収150万以下の場合は63万円の控除がそのまま、年収150万~188万円(新設:特定親族特別控除)では段階的に控除額が減り、年収188万円を超えるとゼロになります。
| 扶養親族の給与 | 所得 | 控除の種類 | ~令和6年 | 令和7年~ |
|---|---|---|---|---|
| ~123万円 (改正前103万) | ~58万円 (改正前48万円) | 扶養控除 | 63万円 | 63万円 |
| ~150万円 | ~85万円 | 特定親族特別控除 (新設) | 0円 | 63万円 |
| ~155万円 | ~90万円 | 61万円 | ||
| ~160万円 | ~95万円 | 51万円 | ||
| ~165万円 | ~100万円 | 41万円 | ||
| ~170万円 | ~105万円 | 31万円 | ||
| ~175万円 | ~110万円 | 21万円 | ||
| ~180万円 | ~115万円 | 11万円 | ||
| ~185万円 | ~120万円 | 6万円 | ||
| ~188万 | ~123万円 | 3万円 | ||
| 188万円~ | 123万円~ | 0円 |
※配偶者の控除には、扶養する本人の所得要件がありますが、特定親族特別控除には本人の所得要件はありません。
控除によってメリットを受けるのは親御さんのみですが、学生にとっても「親に迷惑をかけずにバイトできるライン」が広がるため心理的ハードルが下がる利点があります。結果的に学生アルバイトも以前よりシフトに入ってくれやすくなる可能性があり、中小企業にとっても人手確保につながるプラスの効果が見込まれます。
18歳以下、23歳~69歳の扶養親族
特定親族特別控除の適用はありません。(一般の控除対象扶養親族)
給与123万円以下(所得金額が58万円以下)の場合、38万円の控除とされています。
※従来は給与103万円以下(所得金額が48万円以下)となっておりましたが、基礎控除と給与所得控除の引き上げの影響により20万円限度額が増えています。
配偶者の控除は?
基礎控除と給与所得控除の引き上げの影響により、配偶者控除の年収の限度額が引きあがっています。
※配偶者控除:配偶者の年収123万円以下(所得58万円以下)に改正
社会保険はどうなっている?
所得税の改正で「税金がかからない範囲」は広がりましたが、健康保険・年金の扶養としての年収要件は現行のままです。
社会保険の壁
社会保険の壁とは、パートやアルバイトなどの短時間労働者が一定の年収を超えると社会保険料の負担が生じ、手取り収入が減少するため、労働時間や収入を調整する現象を指します。主な「壁」には以下の2つがあります。
- 106万円の壁:週の所定労働時間が20時間以上で、従業員数51人以上の企業に勤め、月額賃金が8.8万円(年収約106万円)以上の場合、社会保険への加入が義務付けられます。これにより、健康保険料や厚生年金保険料の負担が発生し、手取り収入が減少する可能性があります。
- 130万円の壁:年収が130万円を超えると、勤務先の規模や労働時間に関係なく、配偶者の扶養から外れ、自身で社会保険に加入する必要があります。これにより、保険料の全額を自己負担することになり、手取り収入が減少します。
106万円の壁の撤廃に向けた動き
2026年10月をめどに、年収の要件(106万円)を撤廃
2027年10月をめどに、企業規模要件(51人以上)を撤廃
これらが撤廃されると、賃金の額にかかわらず、週に20時間以上働くと、厚生年金に加入し、保険料を支払う必要が出てきます。
実現すると、将来の年金額が増えるメリットがある一方、手取りが減少する新たな壁となってくる可能性があります。また、雇用主は保険料を折半負担する必要があり、大きな負担を強いられます。
また、これまで対象外だった個人事業所についても5人以上の従業員がいる場合は、2029年10月から加入の対象とする方向です。
一連の見直しで、新たにおよそ200万人が厚生年金の加入対象になる見込みだとしています。
政府の支援策
政府は、これらの「年収の壁」を意識せずに働ける環境を整えるため、「年収の壁・支援強化パッケージ」を実施しています。主な対策は以下のとおりです。
- キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース):事業主が新たに社会保険の適用を行った場合、労働者1人あたり最大50万円を助成します。これにより、社会保険料の負担増加を理由に手取り収入が減少しないよう、事業主が手当を支給することを促進しています。
- 一時的な収入増加への対応:繁忙期などで一時的に収入が増加し、年収が130万円を超えた場合でも、事業主がその旨を証明することで、引き続き被扶養者として認定される仕組みを設けています。
- 配偶者手当の見直し支援:企業が配偶者手当の支給要件を見直す際の手順を示すフローチャートなど、わかりやすい資料を提供し、見直しを促進しています。
まとめ
今回の令和7年度税制改正は、これまで「103万円の壁」に悩んできた多くのパート・アルバイト従業員にとって、働きやすさがぐっと広がる大きな見直しとなりました。それにより中小企業側でも、人手確保やシフト調整の自由度が高まり、経営の選択肢が増える好機になるはずです。
とはいえ、社会保険の加入要件や助成金など、気を付けるポイントも多いのが現実。今回の改正を機に、自社の給与設定や就業ルールを見直し、従業員が無理なく安心して働ける環境づくりを進めていきましょう。
「働きたい人が働ける環境」を整えることが、これからの人手不足時代を乗り越える大きな武器になります。