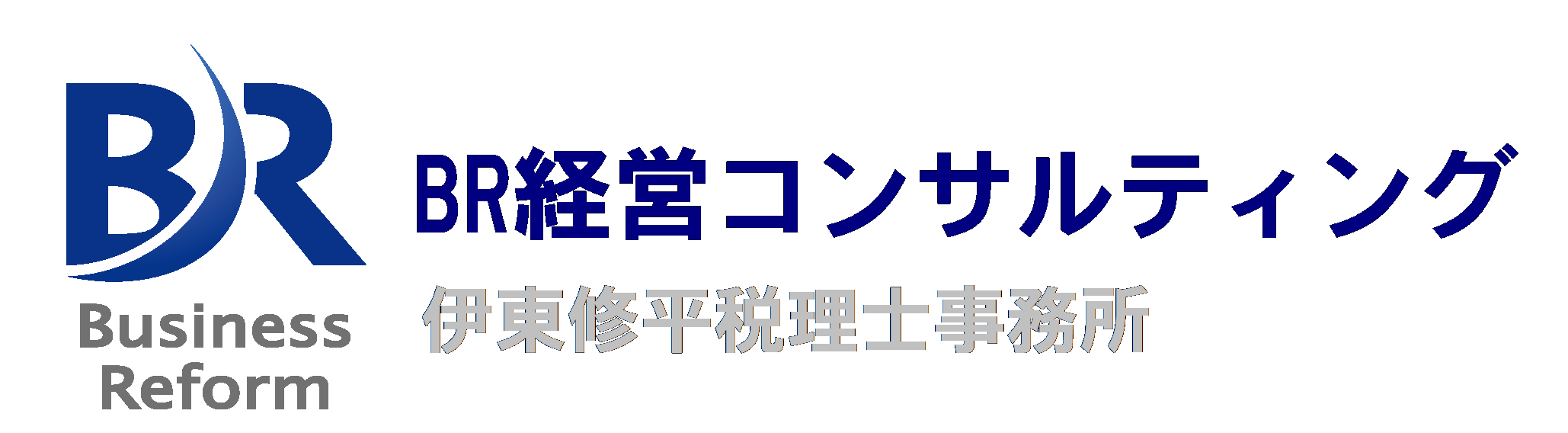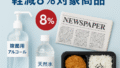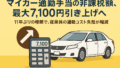中古で購入した機械・車両・パソコンなどは、新品と同じ耐用年数ではなく、
「中古資産専用の耐用年数ルール」に基づいて減価償却する必要があります。
この記事では、国税庁の「中古資産の耐用年数(No.5404)」に基づき、
中古資産の耐用年数の正しい計算方法を、例題つきでわかりやすくまとめます。
◆ 中古資産の耐用年数は「見積法」または「簡便法」
中古資産は以下のいずれかで耐用年数を決めます。
- 見積法(原則)
→ 今後使用可能と見込まれる期間で耐用年数を決める - 簡便法(見積が困難な場合)
→ 多くの中小企業で利用される実務的な方法
※国税庁 No.5404 に定められた計算式
この記事では、実務でよく使われる 「簡便法」 を中心に解説します。
◆ 中古資産の耐用年数(簡便法)の計算式
中古資産の耐用年数は、経過年数がどれだけあるかで計算式が変わります。
① 法定耐用年数の全部を経過した資産(=完全に使い切った中古資産)
耐用年数 = 法定耐用年数 × 20%
※1年未満は切捨て
※2年未満の場合は「2年」にする
② 法定耐用年数の一部を経過した資産(=まだ残存期間がある中古資産)
耐用年数 =(法定耐用年数 − 経過年数)+(経過年数 × 20%)
※1年未満は切捨て
※2年未満の場合は「2年」にする
◆耐用年数の考え方
- 経過年数が大きいほど耐用年数は短くなる
- ただし、どんなに古くても「1年」ではなく 最低2年
- 法定耐用年数を超えているような古いものは「20%ルール」適用
◆ 実例で理解
中古の乗用車を購入した場合
- 法定耐用年数:6年
- 経過年数:3年
- 取得価額:150万円
▼ 計算(法定耐用年数の一部を経過した中古資産)
耐用年数
=(6 − 3)+(3 × 20%)
= 3 + 0.6
= 3.6 → 切捨て「3年」
▼ 結果
耐用年数は 3年
※最低2年ルールは超えているためそのまま3年でOK。
法定耐用年数を超えた古いパソコンの場合
- 法定耐用年数:4年
- 経過年数:5年(=法定耐用年数を経過)
- 取得価額:8万円
▼ 計算(法定耐用年数の全部を経過した中古資産)
耐用年数
= 4年 × 20%
= 0.8 → 切捨て「0年」
→ 最低耐用年数ルールにより 2年
▼ 結果
耐用年数は 2年
◆ よくある質問(FAQ)
Q. 中古資産は「1年」で償却できますか?
できません。
中古資産の耐用年数は 最低2年 と決まっています。
Q. 中古なら定額法を選べますか?
Q. 中古なら定額法を選べますか?
A. 中古だからという理由だけで、自由に定額法へ変更できるわけではありません。償却方法は、資産の種類と税務署への届出ルールに従って決定されます。
1. 資産の種類によって使える償却方法が決まる
償却方法は「中古かどうか」ではなく、資産の種類ごとに適用できる方法が決まっています。
| 資産の種類 | 選択可能な償却方法 |
| 建物・建物附属設備・構築物 | 定額法のみ |
| 機械装置・器具備品・車両運搬具 | 定額法 または 定率法(200%定率法) を選択可能 |
結論: 「中古だから定額法」という考え方は誤りで、資産区分のルールが優先されます。
2. 複数の償却方法を選べる資産は、税務署への届け出が必要
定額法と定率法のいずれかを選べる資産(機械装置、器具備品など)の場合、会社側が希望する償却方法を税務署へ届け出て決定します。
- 中古資産の取得時: 初めてその資産区分(例:これまでは持っていなかった機械装置)を取得する場合、事業の用に供した日の属する確定申告期限までに届け出れば、希望の償却方法を選択できます。
- 途中での変更: 一度届け出た償却方法を、自己判断で勝手に変更することはできません。原則として、事前に税務署長の承認が必要です。
3. 届け出をしない場合は「法定償却方法」が自動で適用される
届け出がない場合、法律で決まっている「法定償却方法」が自動で適用されます。
| 事業者区分 | 選択可能な資産の法定償却方法 |
| 法人 | 200%定率法 |
| 個人事業主 | 定額法 |
中古資産を買っても、届け出をしなければ自動的に法定方法で償却されるため注意が必要です。
4. 誤った償却方法を使うと、申告時に調整が必要になる
税法に定められていない償却方法を使ったり、本来と異なる方法で償却費を計上した場合は、以下の通り処理されます。
- 多く計上した場合: 本来より多く償却費を計上した部分は、税務申告時に経費として否認(減算)されます。
- 少なく計上した場合: 少なく計上した分を、後からまとめて償却することはできません。
償却方法の選択ミスはその年の税額に直結するため、非常に重要な項目です。
Q. リースアップ品(中古)も中古資産扱い?
はい。一般的には中古資産として簡便法を使えます。
◆ まとめ
- 中古資産の耐用年数は「見積法 or 簡便法」
- 実務ではほとんどが「簡便法」を採用
- 経過年数に応じて計算式が変わる
- 最低耐用年数は 必ず2年
- 中古資産は節税・キャッシュフロー改善に有効