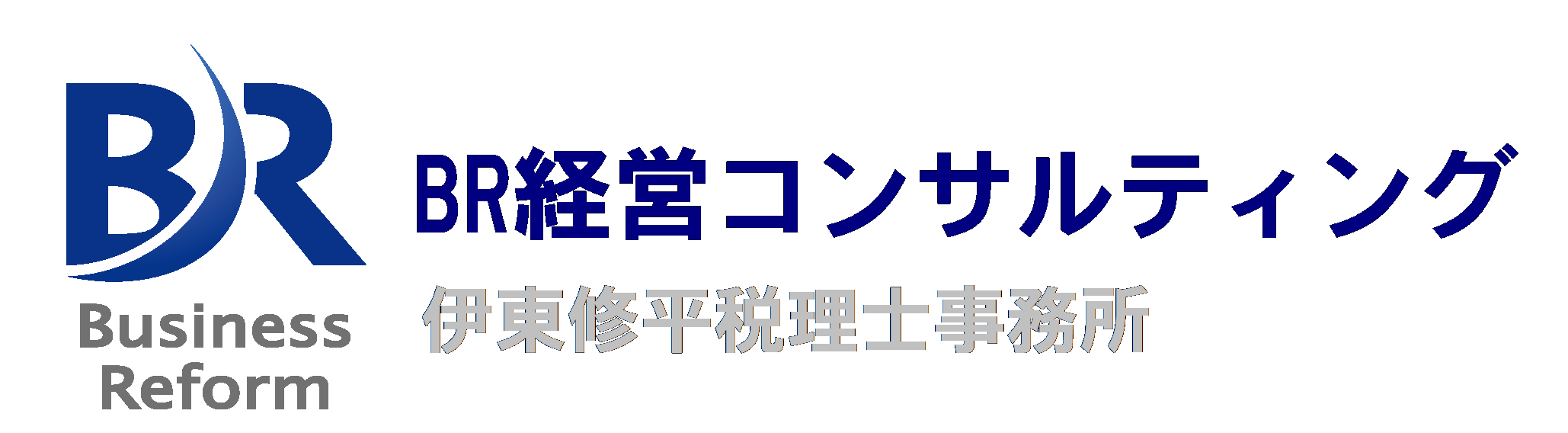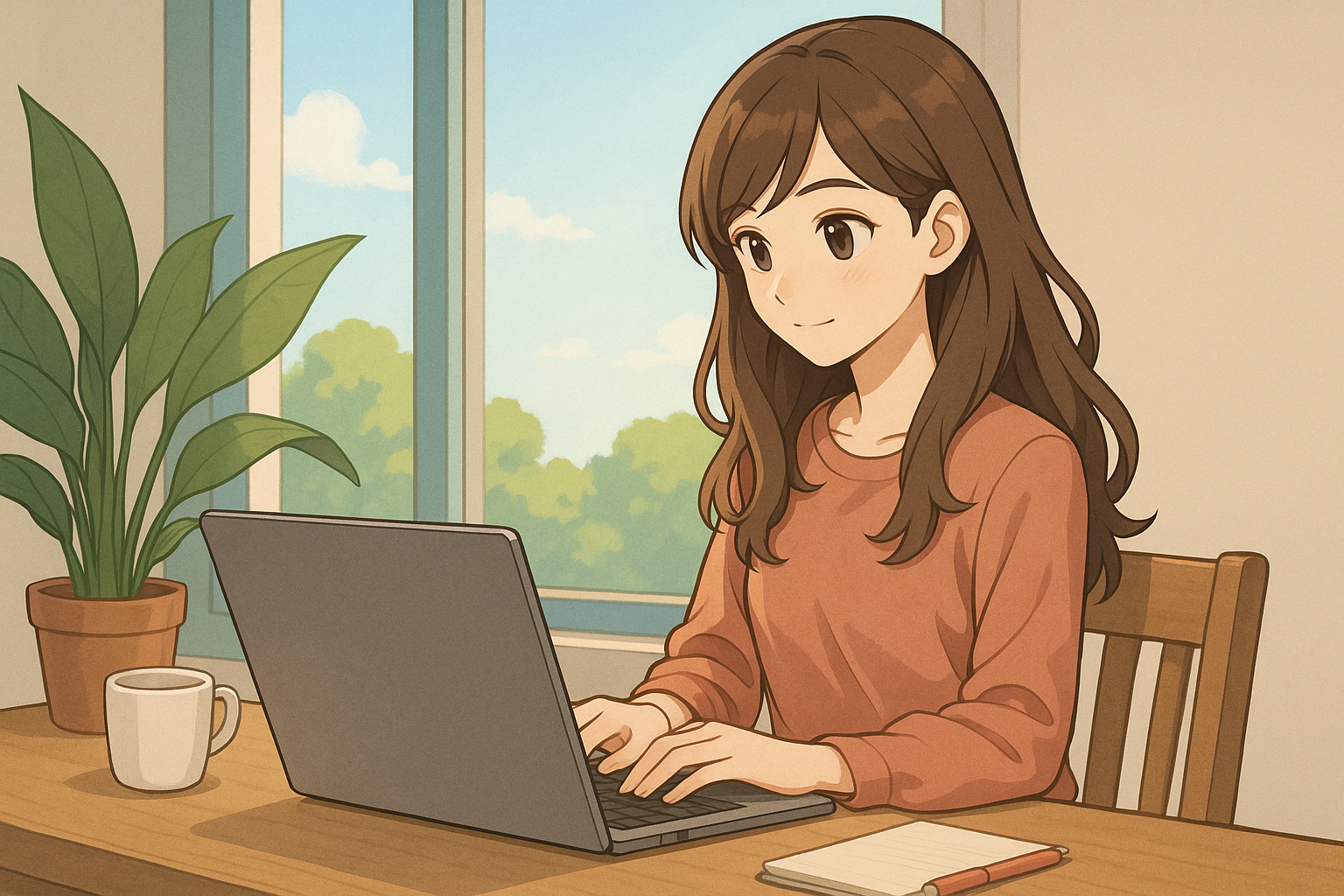フリーランスや個人事業主になったものの、国民健康保険や国民年金などの社会保険料の高さに驚いた方は少なくないでしょう。
「せっかく独立したのに、手取りが思ったより少ない…」
そんな悩みを解消する一つの方法が 「マイクロ法人」 です。
実は、法人化してマイクロ法人を設立するだけで、社会保険料を月数万円単位で節約できる可能性があります。この記事では、その具体的な仕組みと活用術をわかりやすく解説します。
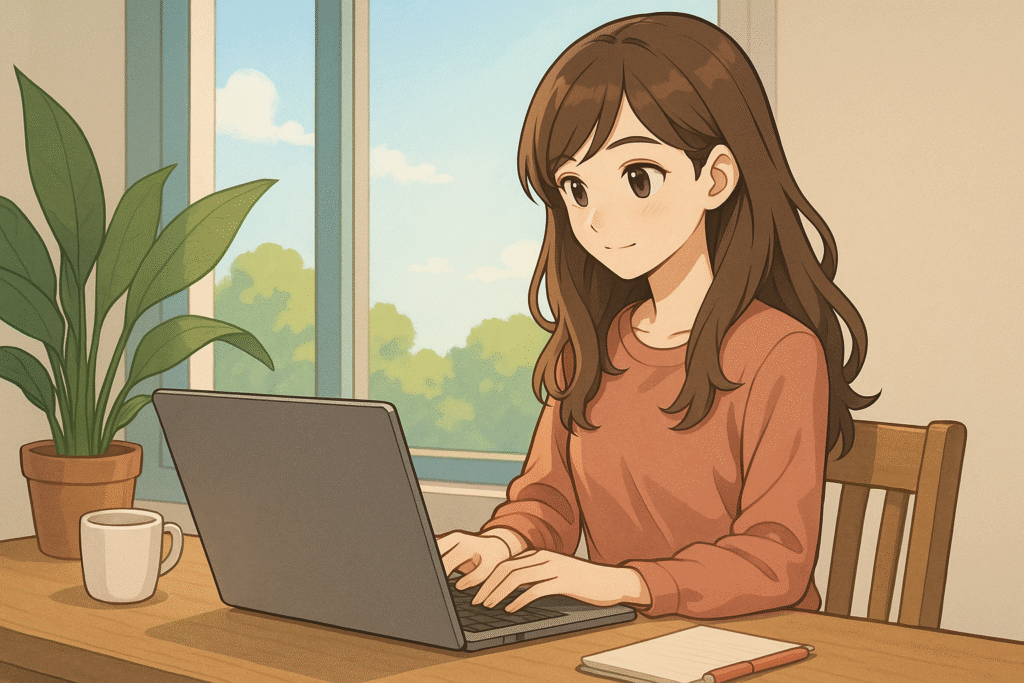
マイクロ法人とは?
マイクロ法人とは、家族経営や一人社長が中心の小規模法人を指します。従業員数0~数名で設立し、以下のような目的で活用されます。
- 税金や社会保険料の節約
- 取引先や金融機関からの信用確保
- 将来の資金調達の可能性拡大
一方で、実体のない「ペーパーカンパニー」は税務署に否認されるなどのリスクが生じる可能性があることから、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
フリーランスと会社員の社会保険の違い
フリーランスと会社員(法人化後)では、加入する社会保険に大きな違いがあります。
| 内容 | 会社員 | フリーランス |
|---|---|---|
| 健康保険 | 協会けんぽまたは健康保険組合(扶養あり・会社折半) | 国民健康保険(扶養なし・全額自己負担) |
| 年金 | 厚生年金(報酬比例+扶養あり) | 国民年金(定額) |
| 労働保険 | 労災・雇用保険 | 原則なし |
この表からもわかるように、扶養や会社負担がある会社員の方が有利な制度設計になっています。
健康保険の仕組み
会社員の健康保険は、給与に応じて標準報酬月額が決定され、標準報酬月額×料率で算定されます。標準報酬月額は58,000円~1,390,000円の50段階とされており、保険料は東京都だと9.91%(40歳以上の場合、介護保険と併せて11.5%)となっています。
会社員の健康保険では会社と本人が折半負担となりますが、国民健康保険は全額個人負担となることから、会社員時代より負担が重く感じることが多いかと思います。国民健康保険には扶養の概念もないため、世帯人数に応じて保険料も増えることになります。
また、保険料を高く払ったからと言って、受けられるサービスが良くなったりもしません。
年金の仕組み
日本の年金は「2階建て」と呼ばれます。
- 1階:定額の国民年金(保険料・月額 17,510円/2025年現在)
- 2階:収入に比例する厚生年金(保険料率 18.3%、会社と本人で折半)
会社員時代は厚生年金に加入していましたが、フリーランスになると国民年金のみ。配偶者が厚生年金に加入していなければ、配偶者分の国民年金も負担する必要があります。
国民年金の月額は、2025年現在17,510円となっています。
配偶者が厚生年金に加入してない場合には、配偶者の年金の支払いも発生します。
一方、厚生年金の保険料は、健康保険と同様、給与に応じて標準報酬月額が決定され、標準報酬月額×料率で算定されます。標準報酬月額は88,000円~650,000円の32段階とされており、保険料は18.3%となっています。
配偶者が扶養に入る場合には、配偶者の年金の負担は生じません。
社会保険の削減のスキーム
マイクロ法人を設立し、役員報酬を 最低限(例:6万円) に設定すると…
- 健康保険料(40歳未満):全額 5,747円(本人負担 2,873円)
- 厚生年金保険料:全額 16,104円(本人負担 8,052円)
合計して本人負担は 月1万円強に抑えられます。(会社負担分は法人の経費になります!)
一方で、フリーランスのままなら、
- 国民健康保険(前年所得に応じ数万円~十数万円/月)
- 国民年金(17,510円/月)
となり、比較すると 月数万円単位での節約 が可能です。
さらに、扶養親族を「協会けんぽの扶養」に入れれば、家族分の国保や国民年金の支払いが不要になり、節約効果はより大きくなります。
加えて、国民年金のみの場合よりも、わずかではありますが2階建て部分の報酬比例の厚生年金も発生するため、将来の給付も増えることとなります。
注意点とリスク
マイクロ法人にはメリットだけでなく注意点もあります。
- 法人設立・維持コスト(登記費用・決算申告費用など)がかかる
- 将来の給付が増やしたいなら、しっかり役員報酬をとり社会保険料を払うほうが良い
まとめ
マイクロ法人は、フリーランスや個人事業主にとって 「社会保険料を抑えつつ制度的に有利な立場を確保する」 有効な手段です。
- 扶養家族がいる方
- 国保・国民年金の負担が重い方
- 節税も同時に検討したい方
には特にメリットがあります。
ただし、法人維持コストや将来の年金額への影響も踏まえ、専門家に相談してしっかり設計をしましょう。
報酬を多く確保したい場合には賞与の社会保険の上限額を活用したスキームもありますが、それはまたの機会に。