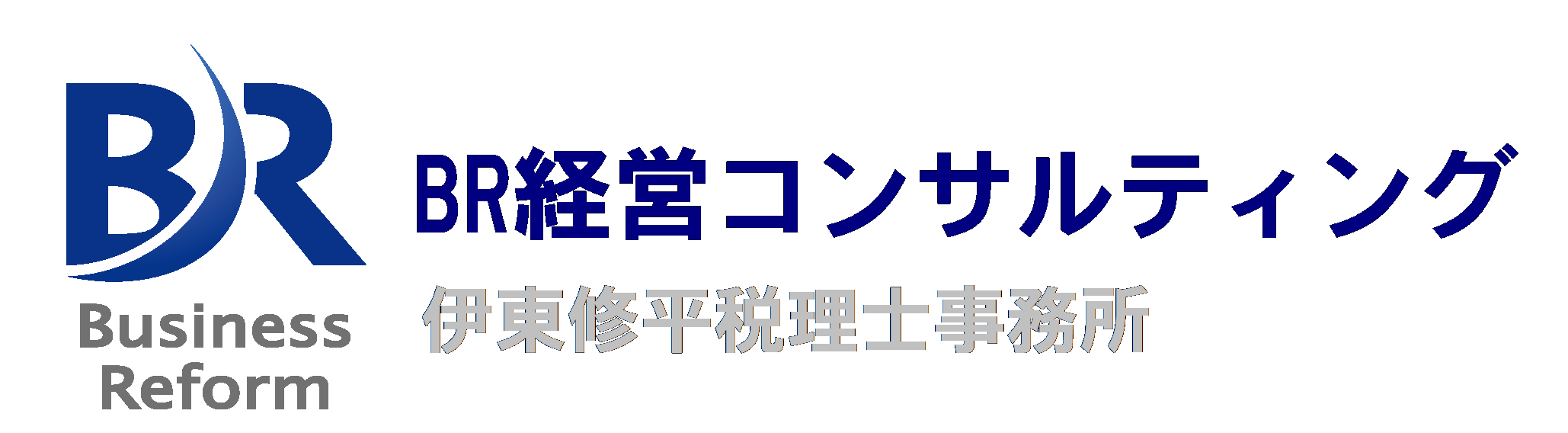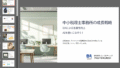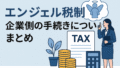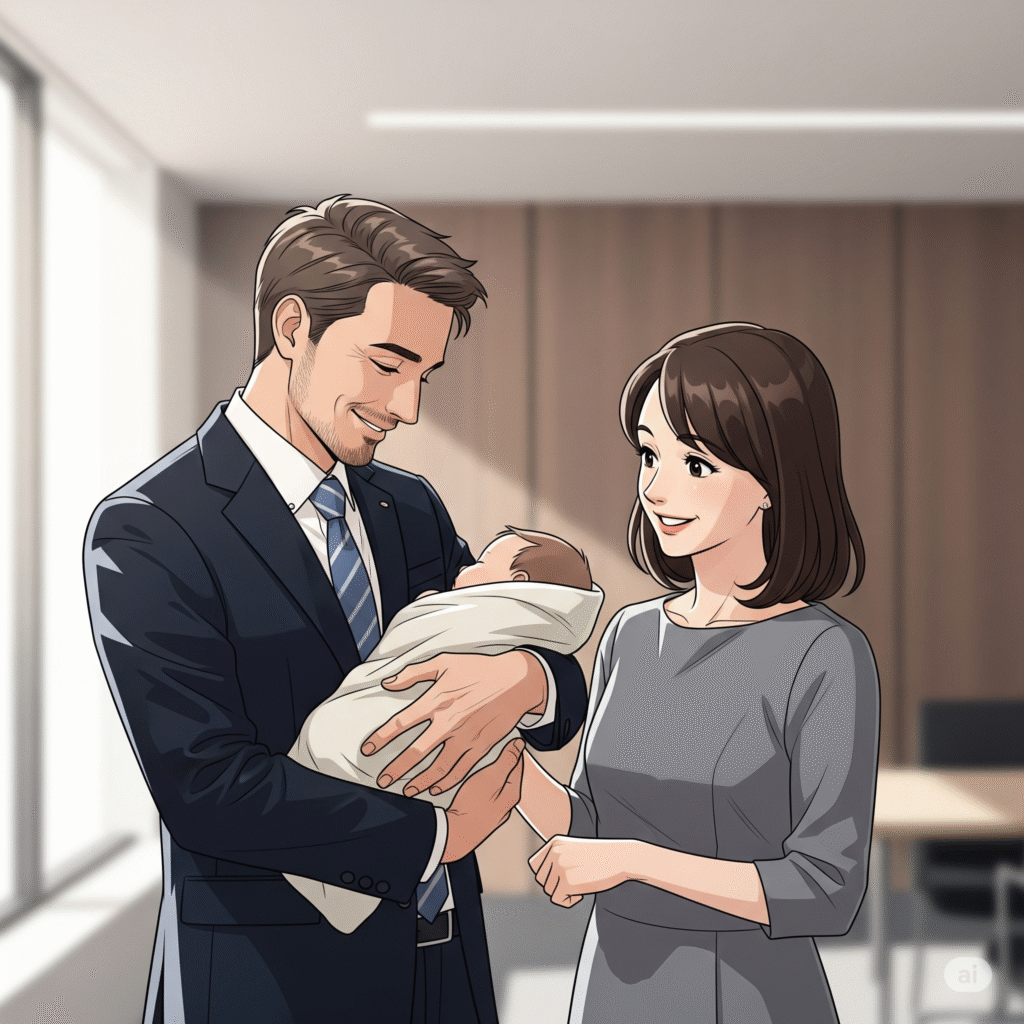
はじめに
会社の役員が産休や育休を取得することになったとき、「報酬を減額したら税務上は問題ないのだろうか?」「手続きはどうすればいいんだろう?」と悩んでいませんか?
役員報酬は原則として、期中の変更が認められていないため、経営者としては不安になりますよね。しかし、産休や育休は例外として認められており、正しく手続きすれば問題ありません。
今回は、役員の産休・育休で報酬を変更する際に知っておきたい、法人税のルールと手続きのポイントをわかりやすく解説します。
1. 役員報酬の基本ルールと、産休・育休が「例外」である理由
役員報酬は「定期同額給与」のルールに基づき、毎月同じ金額を支払うのが原則です。期首から3ヶ月以内の変更を除き、途中で報酬額を変えると、変更した分の金額が会社の損金として認められない(税務上の経費にならない)可能性があります。
しかし、産休や育休は「臨時改定事由」という、やむを得ない事情に該当するため、例外的に認められています。 具体的には、産休・育休によって、役員が本来の業務を継続できなくなる「業務内容の質的な変化」があったと見なされるため、報酬の減額や支給停止をしても、損金として算入できるのです。
2. 減額・停止する際の手続きは必須!議事録を必ず残しましょう
報酬の変更を税務上問題なく行うためには、正式な手続きが必要です。
- 取締役会または株主総会での決議:報酬の減額や支給停止を行う際は、取締役会または株主総会で正式に決議しなければなりません。
- 議事録の作成と保存:決議した内容は必ず議事録として記録し、保管しておきましょう。これにより、税務調査が入った際にも、なぜ報酬を変更したのかを明確に説明できます。
この手続きを怠ると、せっかく減額しても損金算入が否認されるリスクがあります。
3. 注意!報酬の日割り支給はNGです
産休や育休に入る月、または復帰する月で、報酬を日割り計算して支給するのは避けてください。 日割り支給をすると「定期同額給与」の原則に反するため、税務リスクが生じる可能性があります。 報酬を変更する場合は、「〇月分からは全額支給停止」あるいは「〇月分からは満額支給」のように、区切りを明確にすることが重要です。
4. 減額で受けられる「社会保険料の免除」と「出産手当金」
役員報酬を減額または停止することで、以下の給付制度や免除制度を活用できる可能性があります。
- 社会保険料の免除: 産前産後休業期間中は、役員本人と会社負担分の社会保険料が免除されます。これは、保険料負担がなくなる大きなメリットです。
- 出産手当金: 報酬を減額または停止することで、健康保険から出産手当金が受け取れる場合があります。支給額は、標準報酬額(報酬を基準に計算される額)に基づき、1日あたり約2/3が目安です。
特に注意すべきは出産手当金です。 役員報酬が一定額以上だと、出産手当金は支給されません。そのため、受給を検討する場合は、報酬の減額や停止が重要なポイントになります。
5. まとめ:役員の産休・育休で報酬を変更する際のチェックリスト
| 項目 | 内容 |
| 例外の根拠 | 産休・育休は「臨時改定事由」に該当するため、報酬の減額や停止は損金算入が可能。 |
| 必須の手続き | 取締役会や株主総会で決議し、議事録を必ず作成・保管する。 |
| 日割り支給 | 税務リスクがあるためNG。満額支給か支給停止かを明確にする。 |
| 給付・免除 | 報酬を減額することで、社会保険料免除や出産手当金が受けられる可能性がある。 |
最後に
役員報酬の変更は、法人税だけでなく、社会保険料や給付金制度など、複数の専門知識が必要な複雑な手続きです。
「本当にこの方法で大丈夫だろうか?」 「自社のケースではどうすればいい?」
もし少しでも不安を感じられたら、ぜひ当事務所にご相談ください。
状況に合わせた最適な手続き方法をご提案し、税務リスクを回避できるようサポートいたします。
お気軽にお問い合わせください。