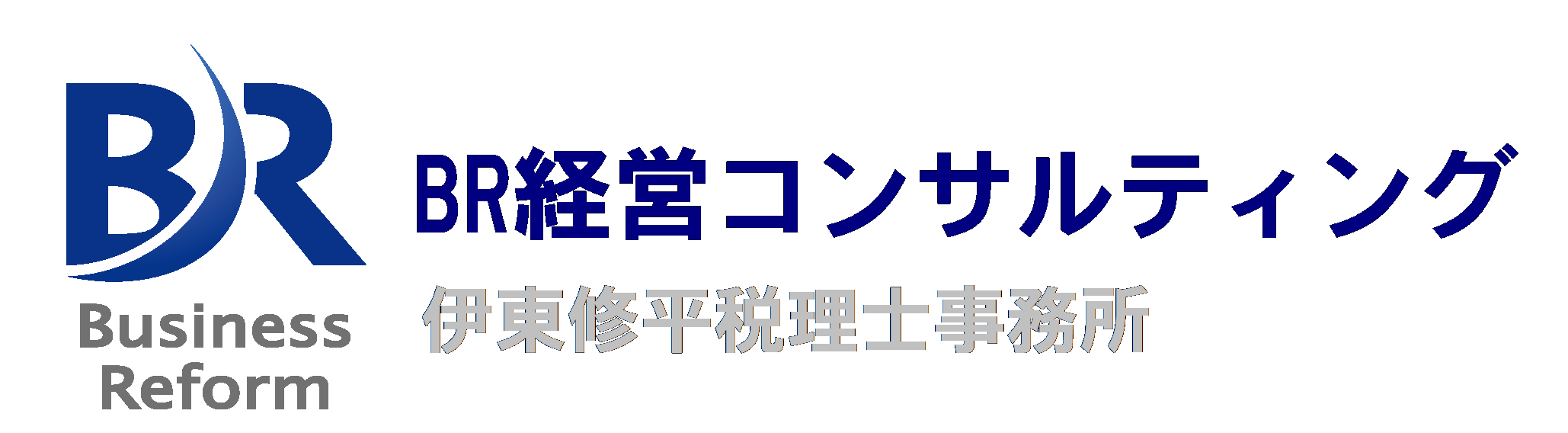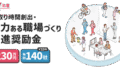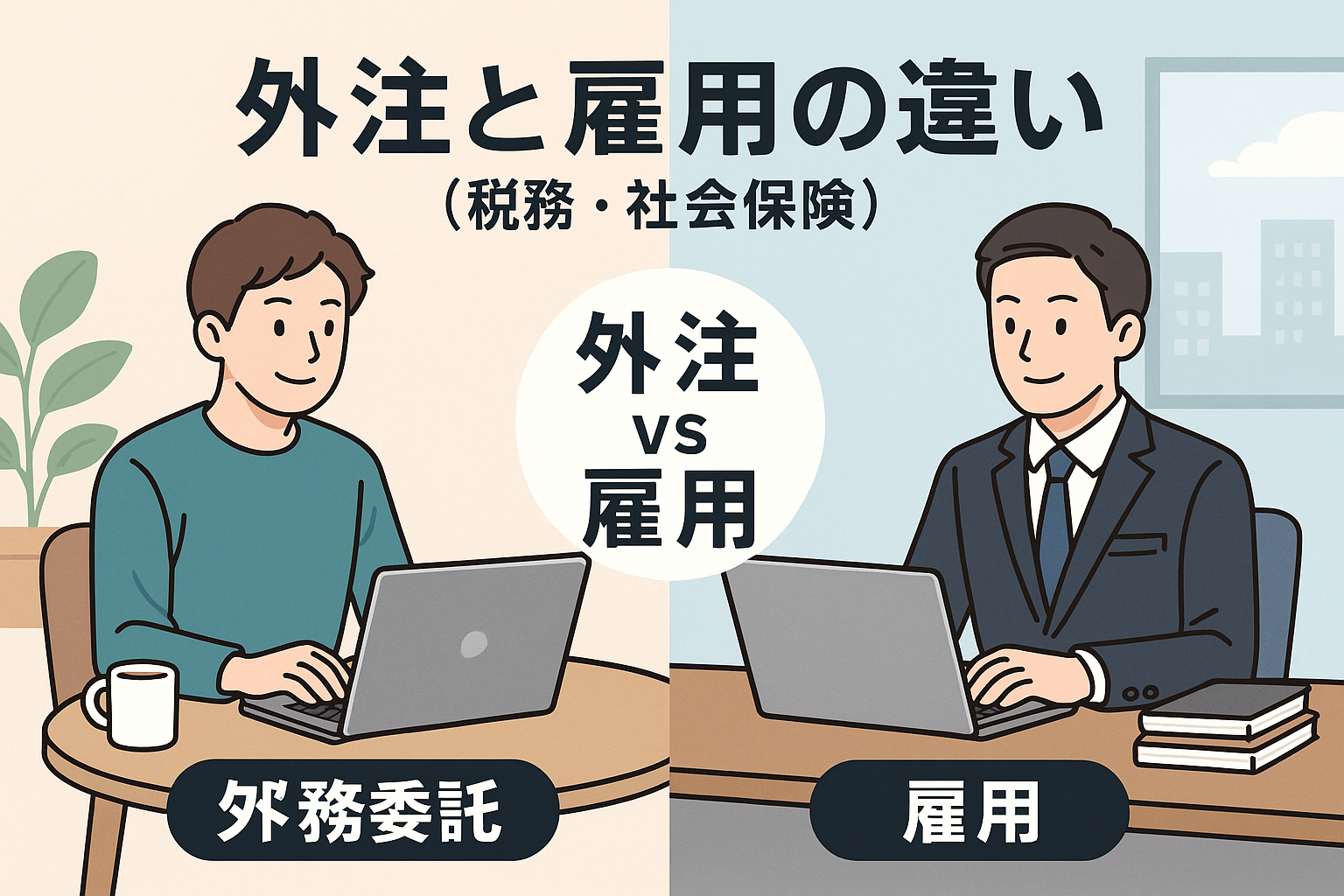
ビジネスの現場では、人材の確保方法として「外注(業務委託)」と「給与(雇用)」の2つがよく比較されます。どちらを選択するかで、企業・個人双方の税務や社会保険の取り扱いが大きく異なります。本記事では、税務と社会保険の観点から、両者の違いをわかりやすく解説します。
外注(業務委託)と給与(雇用)の基本的な違い
| 項目 | 外注(業務委託) | 給与(雇用) |
|---|---|---|
| 法的関係 | 請負契約・委任契約 | 労働契約 |
| 指揮命令関係 | なし(成果物提供や業務達成が目的) | あり(会社の指示に従う) |
| 勤務時間・場所 | 自由 | 会社指定 |
| 報酬の呼称 | 業務委託料 | 給与・賞与 |
税務上の取り扱い
(1)企業側の取り扱い
支払う企業側にとっては、「消費税の控除ができる」「社会保険料負担がない」など、外注のほうが有利になるケースが多いです。
実体としては雇用なのに業務委託としていてトラブルになるケースもありますので注意が必要です。
- 外注(業務委託)
外部に業務の依頼を行い、その完了をもって対価が支払われるもの、というのが基本的な考え方です。- 支払報酬は外注費等として経費計上。
- 一部の報酬(例:士業報酬など)は源泉徴収義務あり。
- 給与(雇用)
労働契約により、事業主と労働者が給与を支払う契約をします。- 支払給与は給与所得として経費計上。
- 必ず源泉所得税の天引きが必要。
- 年末調整の義務あり。
(2)個人側の取り扱い
- 外注(業務委託)
- 報酬は事業所得または雑所得として確定申告。
- 経費を差し引いて所得を計算できる。
- 給与(雇用)
- 会社が源泉徴収を行い、原則確定申告不要。
- 副業や年収要件によっては確定申告が必要。
社会保険・労働保険の取り扱い
| 項目 | 外注(業務委託) | 給与(雇用) |
|---|---|---|
| 健康保険・厚生年金 | 原則なし(個人事業主として国民健康保険・国民年金に加入) | 会社が加入義務(協会けんぽや健康保険組合+厚生年金) |
| 雇用保険 | 加入なし | 加入義務あり(一定条件以上の労働者) |
| 労災保険 | 原則なし(※特別加入制度あり) | 強制加入 |
判断基準:「雇用か業務委託か」
税務署や労働基準監督署は、契約書の名称ではなく実態で判断します。
以下の点がポイントです。
- 指揮命令関係があるか
- 勤務時間・場所が指定されているか
- 他の業務との兼業が可能か
- 報酬が固定給か成果報酬か
実態が「雇用」に該当すると判断されれば、偽装請負とみなされ、過去分の保険料や税金の追徴が課される場合があります。
国税庁には、以下の通達があります。
(1) その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
(2) 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。
(3) まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。
(4) 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。
結論
外注は柔軟な働き方やコスト削減が魅力ですが、契約内容や実態に十分注意しないと法的リスクが伴います。
給与(雇用)は安定した労働力の確保ができる反面、社会保険や労務管理コストがかかります。
自社の状況や事業方針に合わせて適切な契約形態を選ぶことが大切です。