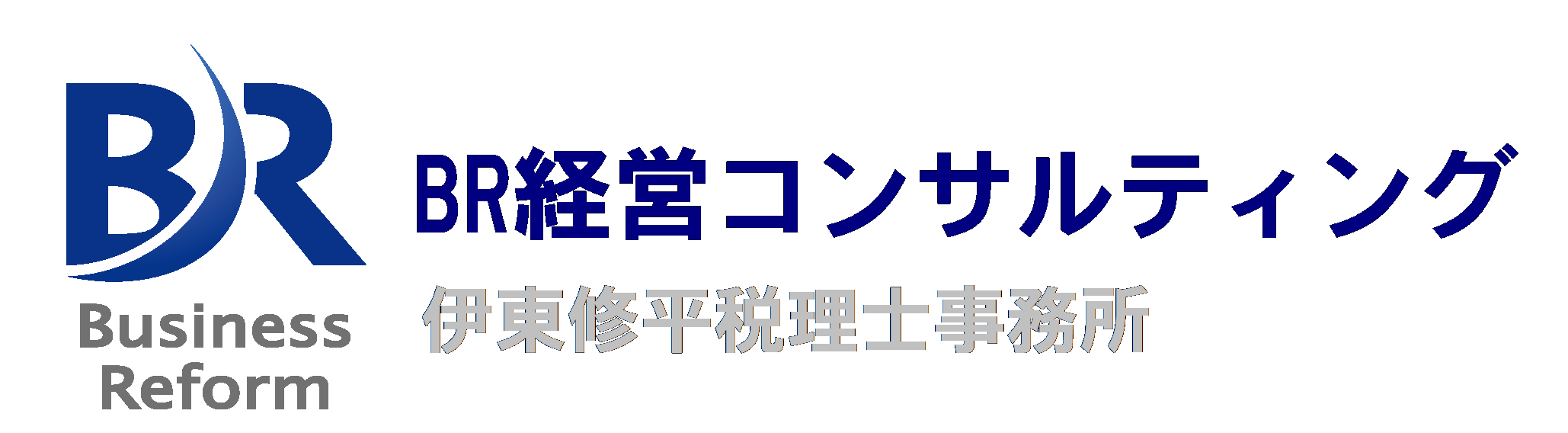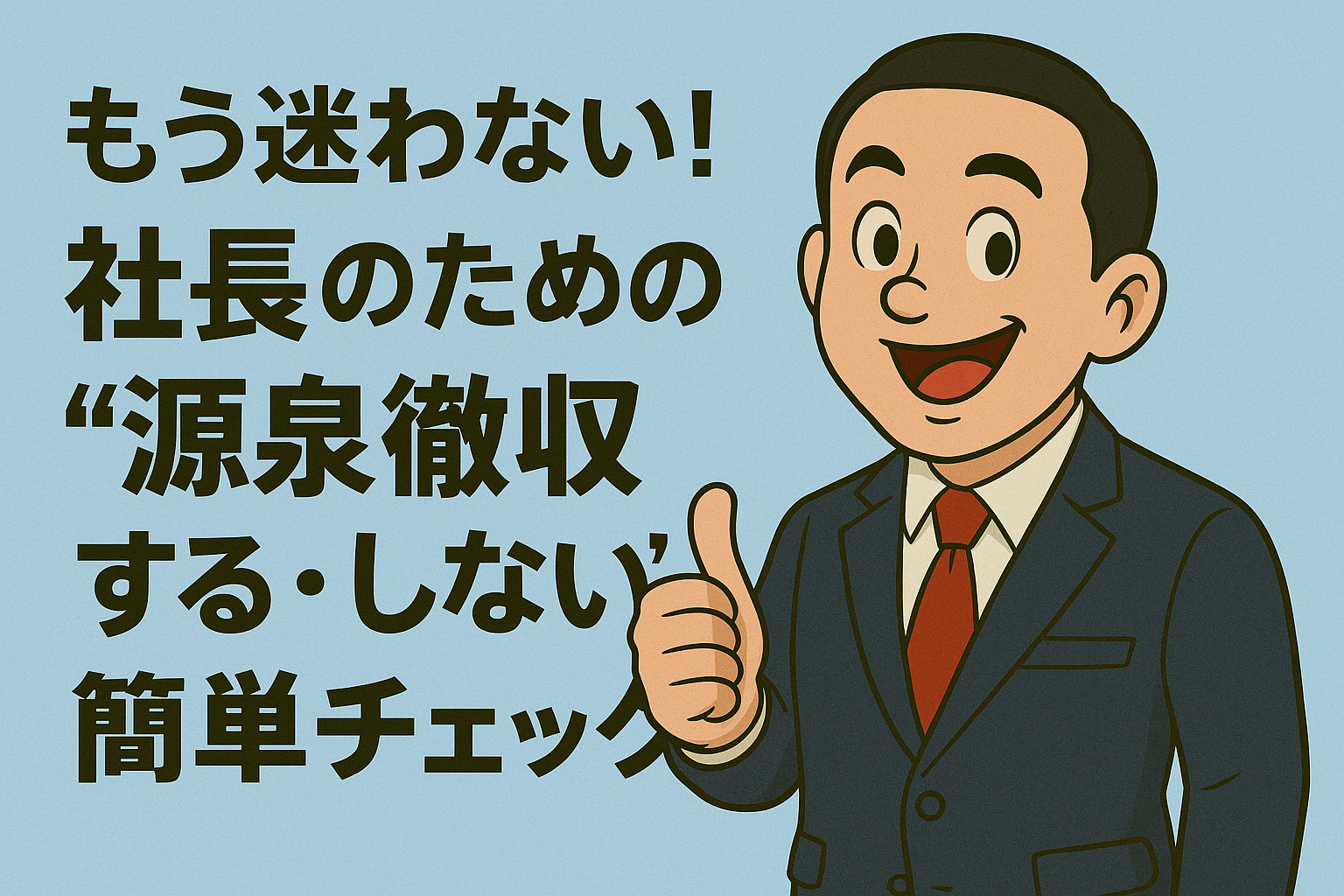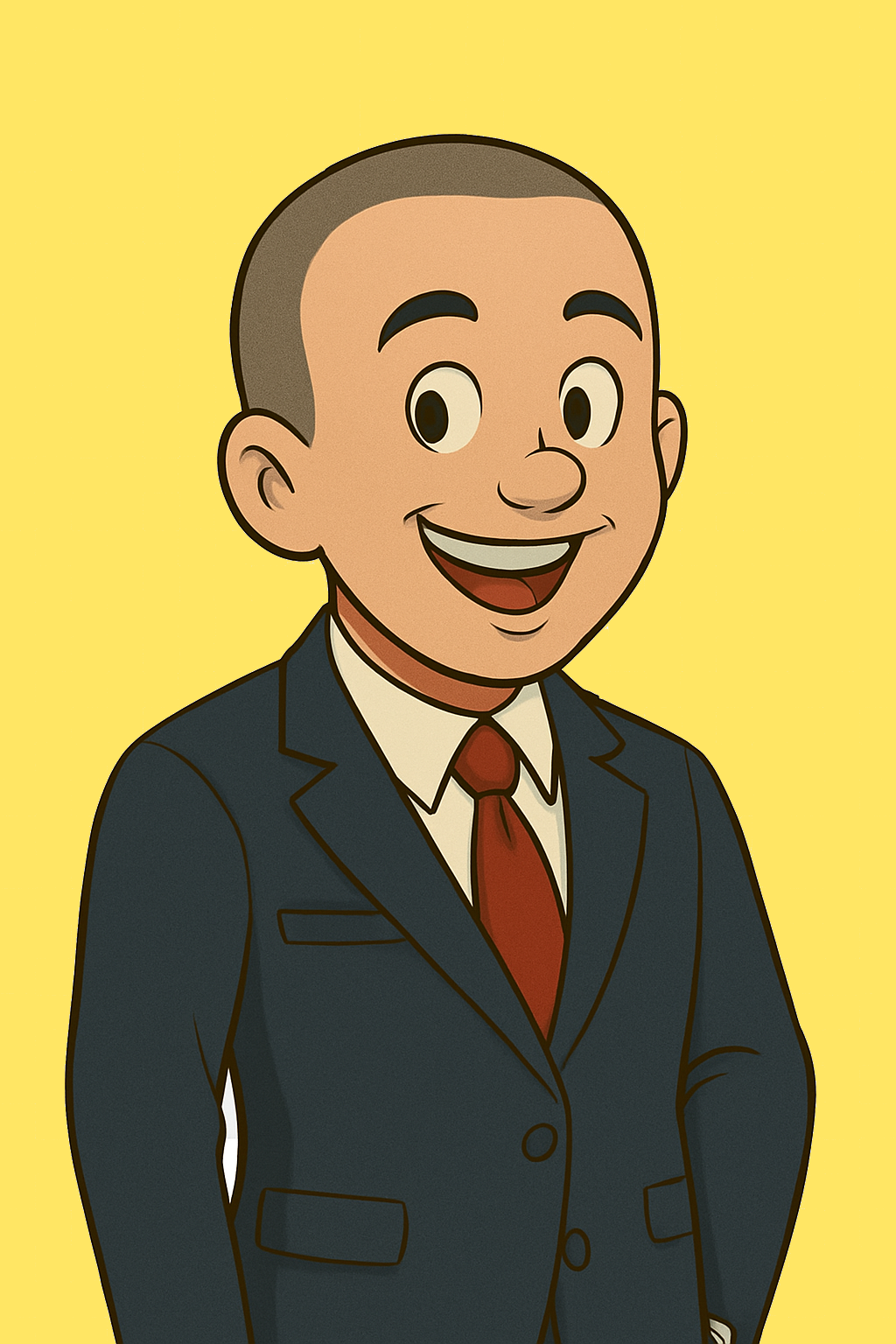
「士業の先生への支払い、源泉って必要だっけ?」 「外注にお願いした仕事、毎回確認が大変…」中小企業の経営者や担当者なら、こんな疑問を感じたことがある方も多いのではないでしょうか?
今回は、中小企業の代表者が押さえておくべき「源泉徴収が必要な報酬」について、わかりやすくまとめました。
そもそも「源泉徴収」とは?
源泉徴収とは、報酬や給料を支払うときに、あらかじめ税金を差し引いて国に納める仕組みのこと。
従業員の給料はもちろん、個人に対する特定の報酬や料金の支払いも対象になります。
さらに、広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金なども源泉徴収の対象になります。
「報酬」ってなに?どんな支払いが対象?
ここでいう「報酬」とは、士業の先生、外注フリーランス、講師などに業務の対価として支払うお金のこと。つまり「人に対する仕事の対価」と考えると分かりやすいです。
■ 源泉徴収が必要な「主な報酬」とは?
| 区分 | 対象となる人 | 税率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 士業報酬(税理士・弁護士など) | 税理士 社会保険労務士 弁護士 司法書士など ※行政書士は源泉不要 ※法人は源泉不要 | 100万円以下:10.21% 100万円超部分:20.42% | 1回の支払いごとに判定 |
| 外注報酬(デザイナー・ライター等) | フリーランスのカメラマン、デザイナー、Web制作等 ※システムエンジニアやプログラマーは源泉不要 | 同上 | 業務請負契約に基づく |
| 講演・講師謝礼 | セミナー講師など | 同上 | 1回でも講義すれば対象 |
| 芸能関係者への報酬 | 役者・演奏家など | 同上 | 広告出演など含む |
| プロスポーツ選手等 | イベント出演等 | 同上 | 一時的でも対象 |
💡 税率は支払い内容によって異なります。
20.42%の税率が適用除外とされている報酬もあります。例)外交員報酬やプロスポーツ選手など
詳細は、国税庁F&Qを参照。
■ 消費税の取り扱いについて
🔍 消費税は、原則として源泉徴収の対象に含まれます(=税込で計算)。
ただし、請求書等で消費税額が明確に区分されている場合には、税抜金額を基に源泉徴収しても差し支えありません(通達上の特例)。
【例1】税込10万円(消費税の記載なし)
→ 10万円 × 10.21% = 10,210円
【例2】報酬90,910円+消費税9,090円(明記あり)
→ 90,910円 × 10.21% ≒ 9,286円
💡 どちらで計算するかは、請求書の記載により判断します。
■ 具体例:こんな時どうする?
Q:フリーのデザイナーにロゴ制作を依頼。請求額は消費税込み10万円。源泉は必要?
👉 Yes!個人事業主への業務委託報酬のため源泉徴収が必要です。
- 【税込記載のみの場合】:10万円 × 10.21% = 10,210円
- 【消費税が明記されている場合】:90,910円 × 10.21% ≒ 9,286円
■ 源泉徴収したらどうすればいい?
✅ 納付のタイミング
| 支払い内容 | 通常の納付期限 | 納期の特例(届出必要) |
|---|---|---|
| 税理士・弁護士など士業報酬 | 翌月10日まで | 年2回(7月と1月)にまとめて納付可 |
| 講師謝礼・原稿料・外注報酬など | 翌月10日まで | 特例は使えません! |
士業報酬は「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」で、給与等と一緒に納付します。
その他の報酬は、納期の特例の承認を受けていたとしても毎月納付が必要です。
(給与・士業報酬とは納付書の種類が違います)
✅ 納付書の種類
- 【士業報酬など(特例対象)】
→ 「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(税目番号:320)」に報酬欄あり - 【講演料・原稿料など】
→ 同じ納付書だが、報酬欄での金額区分に注意
■ 支払調書の作成・提出
- 対象となる報酬について、翌年1月31日までに税務署へ「支払調書」を提出
(提出が必要となる金額の要件などもあります) - 受け取った相手に対しても、控えを交付するのが一般的(義務ではないが推奨)
■ まとめ
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| 誰に払う? | 個人への支払いは要注意(法人は原則不要) |
| 何に対して? | 業務の対価=報酬、特に士業・講師・原稿料等 |
| 税率は? | 内容により異なる。士業の報酬等は、100万円超で超過分20.42% |
| 対象となる報酬の消費税の取り扱い | 原則:税込で源泉計算/明記あれば税抜でもOK |
| 納付は? | 士業報酬=年2回特例あり/それ以外=毎月納付 |
| 調書提出 | 毎年1月末まで。必要に応じて相手方にも控え送付 |
「これって源泉徴収の対象かな?」と迷ったときは、
✅ 個人への支払いか?
✅ 報酬・料金に該当するか?
この2点をまずチェックしましょう。
📎【無料ツール紹介】
弊社では、報酬に関する源泉徴収税額の自動計算ツールをご用意しています。
▶︎ 源泉徴収計算ツールはこちら