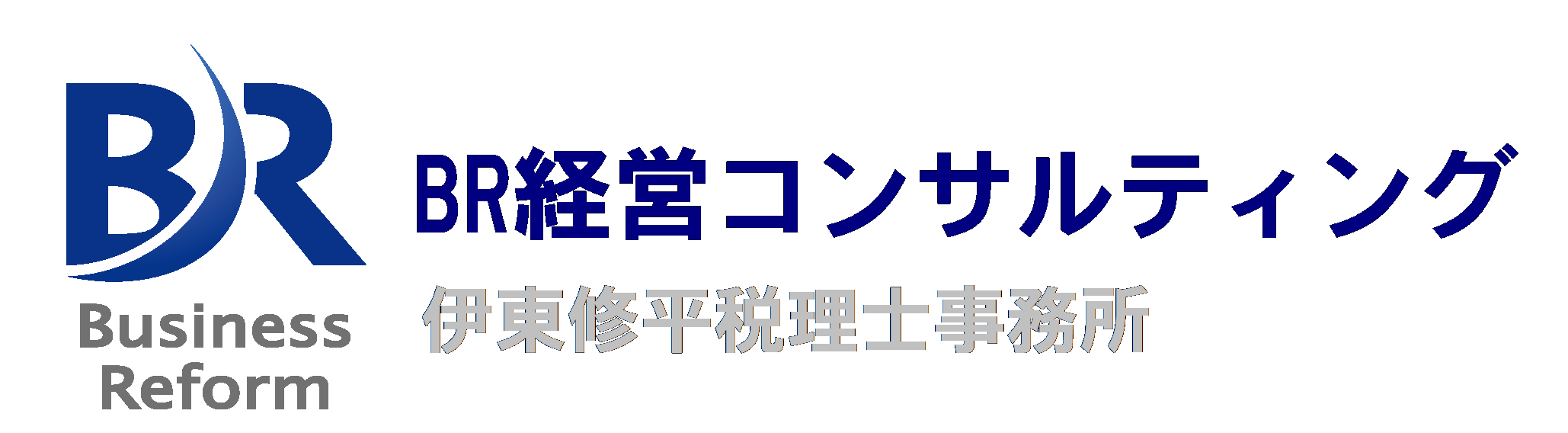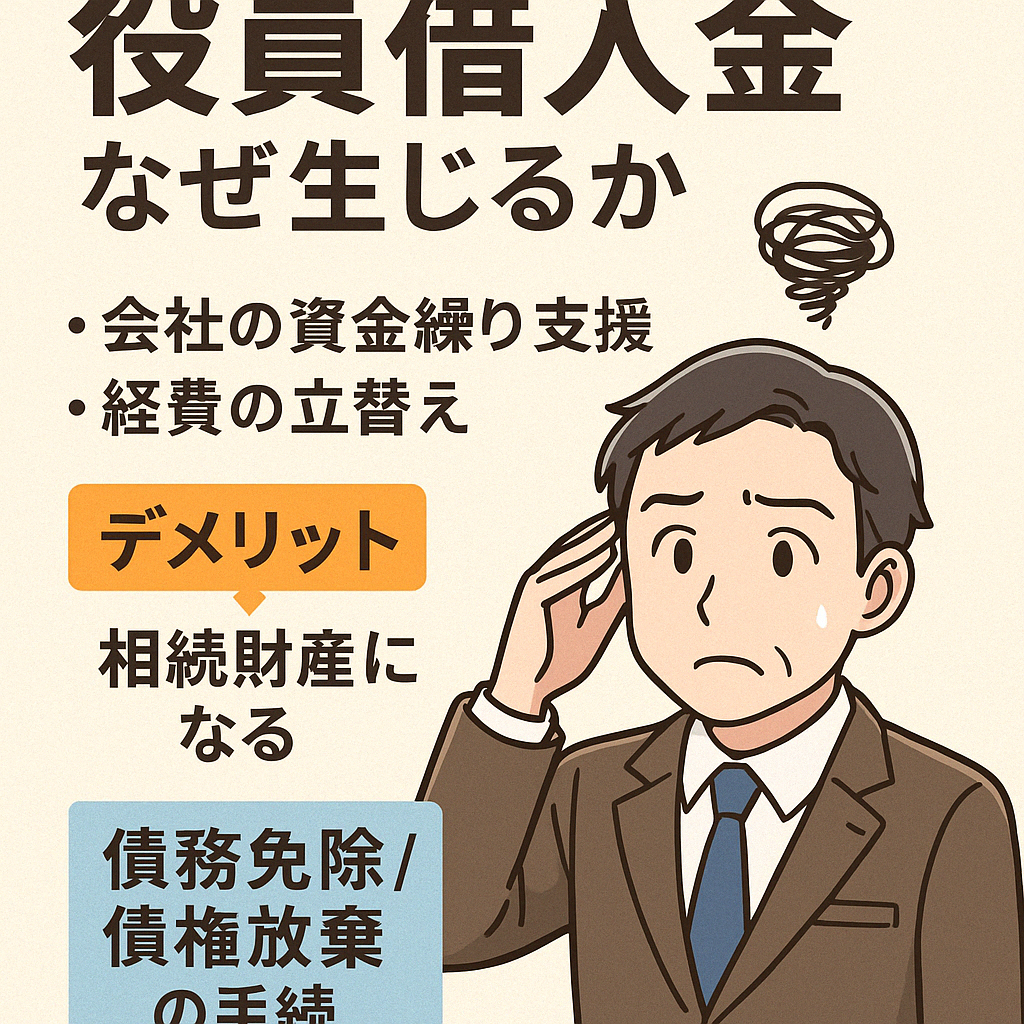中小企業の経営者にとって重要な「役員退職金」についてお話しします。
「役員退職金って経費になるの?」
「いくらまで払っていいの?」
「税務署に否認されるリスクって?」
そんな疑問に、わかりやすくお答えします!
そもそも役員退職金とは?
役員が退任したときに支給される「功労金」のようなもの。
長年の会社への貢献に対する“ねぎらいの報酬”といえます。
従業員の退職金と同じく、原則として会社の「損金(=経費)」になります。
つまり、会社の利益を圧縮して節税につながる、というわけですね。
法人の経費として認められるための3つのポイント
ただし、何でもかんでも払えばOKというわけではありません!
税務署に「これは払いすぎ!」と判断されると、経費にできないことも。
以下の3つの基準がとても重要です。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| ① 支給の必要性 | 本当に退任したのか?誰が見ても自然な退職か? |
| ② 株主総会決議 | 株主総会できちんと支給額を決議しているか?(議事録が必要) |
| ③ 支給額の妥当性 | 「功績倍率」などをもとに適正に計算された金額か? |
本当に退任したのか?の判断
これは、形式的な退任(=実は会社に残って指示を出し続けている)とみなされると、税務上の問題になるからです。
たとえば…
NGなケース
- 表向きは「退任」しているが、実際は毎日出勤し続けている
- 新たに役員ではない「顧問」として、役員時代と同じ仕事を続けている
- 株主総会で退任の決議をしていない(書面がない)
- 後継者に全く権限が移っていない
- 役員報酬が下がっていない(具体的には1/2以上もらっている)
- 従来の名刺をそのまま使い続けている
このような状態だと、「本当に退職したとは言えない」とされてしまい、退職金は“給与”として扱われ、退職所得の税制優遇が受けられないこともあります。
退任後も仕事を継続する場合
役員を退任したとしても、会社で後継者に業務を引き継ぐために仕事をしても問題ありません。
給与を半分以下、登記などの形式も整理、出勤日も減らす、経営に口を出さない、等、上記のNGの例に該当しないようにご注意ください。
支給額の計算方法:功績倍率とは?
退職金の金額は、「最終報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率」で決めるのが一般的です。
例えば、
最終月額が60万円、勤続年数30年、功績倍率が3.0の場合:
60万円 × 30年 × 3.0 = 5,400万円
この「功績倍率」は、一般的に2.0~3.0が妥当と言われています。
代表取締役や創業者は3.0以上でも認められるケースもありますが、高すぎると税務署に否認されるリスクが高まります。
同業種同規模の会社の支給状況や、法人業務従事期間、事情等を考慮して決定しましょう。
役員退職金の課税関係(会社側)
NGなケースに該当しなければ、経費として損金算入できます。
原則
原則として、株主総会の決議等によって退職金の額が具体的に確定した日の属する事業年度又は実際に支給した日の属する事業年度に損金算入します。
分割払い
退職金が高額な場合、一定の要件を満たすことで分割支給もできます。
分割支給する際は、下記の要件を満たしている必要があります。
- 株主総会等で分割支給が決議され、かつ議事録を作成していること
- 資金繰りが厳しいなど分割して支給する合理的な理由があること
- 分割する期間が長期間に渡らないこと
(3)については、分割期間5年以上になると退職年金として取り扱われる可能性があるため、注意が必要です。
分割払いの場合の経理と税務処理
原則
退職金が確定した日に経費処理することになります。
例)3年分割 3000万円
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 退職金 | 30,000,000円 | 未払金 | 30,000,000円 |
| 未払金 | 10,000,000円 | 普通預金 | 10,000,000円 |
※所得税等は省略しています
例外:支払の都度経費にする
『実際に支給した日の属する事業年度』において損金として処理することも認められます。
例)3年分割 3000万円
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 退職金 | 10,000,000円 | 普通預金 | 10,000,000円 |
役員退職金の課税関係(個人側)
役員本人が受け取る退職金には、「退職所得控除」+「1/2課税」という大きな税制メリットがあります!また、分離課税となっているため、他の所得が大きくても税額が変わらないメリットもあります。
【退職所得の計算方法】
(退職金の額 − 退職所得控除)× 1/2(※) = 課税退職所得金額
※法改正により、勤続年数が5年以下の役員については、上記計算式の1/2が適用されませんのでご注意ください。
【退職所得控除額】
| 勤続年数 | 控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数(※最低80万円) |
| 20年超え | 800万円+70万円 ×(勤続年数−20年) |
所得税の税額表〔求める税額=A×B-C〕 (令和6年度)
| A 課税退職所得金額 | B 税率 | C 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
※そのほか、住民税が10%課税されます。
税額の具体例
退職金1000万円、勤続3年の場合
①退職所得金額
1000万円ー40万円×3年=880万円
※勤続5年以下なので、1/2はしない
②税額
所得税額 880万円×23%ー636,000円=1,388,000円
住民税額 880万円×10=880,000円
合 計 2,268,000円
まとめ
適切な運用をすれば、損金算入額も大きく、個人所得税も優遇される退職金は非常に有利な制度です。
不明点等あれば是非ご増段ください。