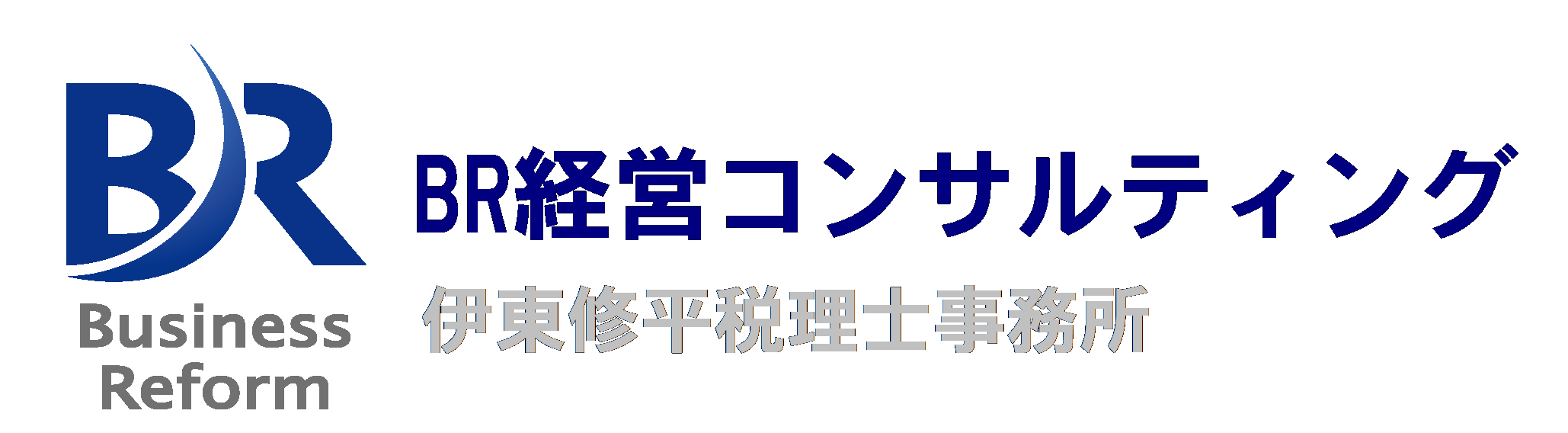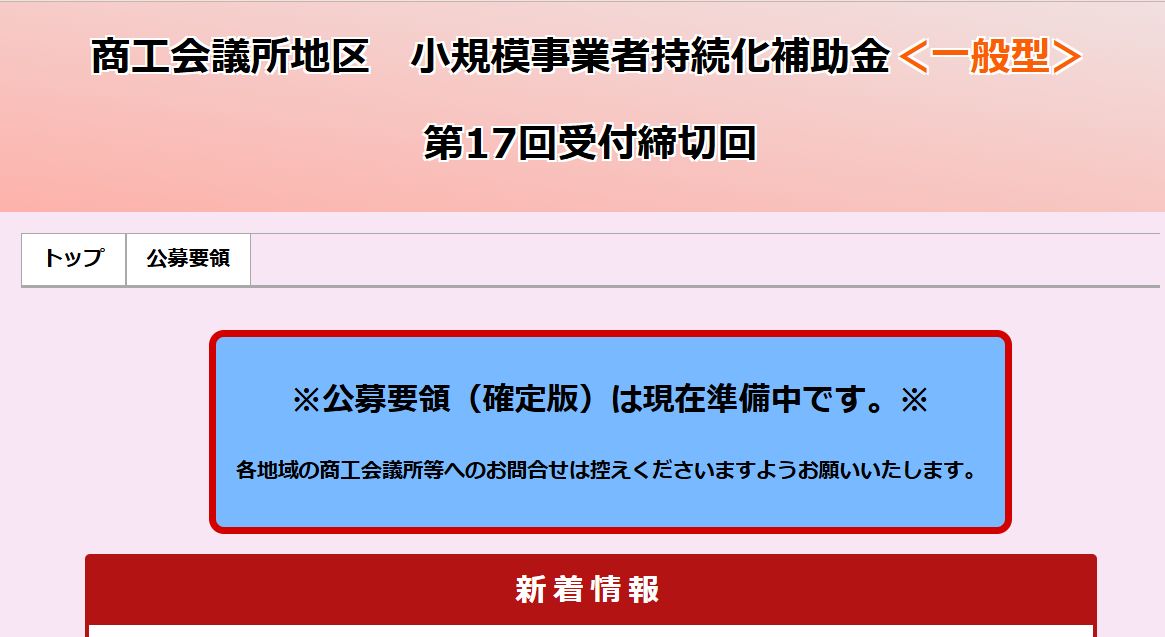小規模事業者持続化補助金とは?
小規模事業者持続化補助金(略して「持続化補助金」)は、小規模企業が販路開拓や業務効率化の取り組みを行う際、その経費の一部を国が支援してくれる補助金制度です。
経営環境の変化(例えばインボイス制度への対応や賃上げなど)に対応するために、自社で経営計画を作成し、その計画に基づいて行う販路拡大や生産性向上の取り組みを応援する目的で設けられています。2025年度版では新たな特例措置も用意され、条件次第で最大250万円もの補助を受けられるチャンスがあります。
今回は、中小企業の経営者の皆さん向けに、2025年の小規模事業者持続化補助金について申請要件や補助内容、使える経費、申請のコツなどを分かりやすくご紹介します。
この記事は、執筆時(2025/3/23)の暫定版の第17回公募要領を基に記述しています。
今後公募要領が修正される可能性もありますので、最新の情報は補助金HPを確認してください。
補助金の内容
補助率・補助額:補助金はいくら出る?特別枠はあるの?
補助金額は、基本的には対象経費の2/3が支給され、補助金の上限額は50万円となります。例えば75万円の経費が認められれば、その2/3である50万円が補助金として受け取れる計算です。補助金は後払い(立替払い)方式で、採択後に実績報告を経て支給される点も覚えておきましょう。
2025年度は、この通常枠のほかにいくつかの特例措置が用意されています。
| 補助率 | 2/3(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は3/4) |
| 補助上限 | 50万円 |
| インボイス特例 | 50万円上乗せ |
| 賃金引上げ特例 | 150万円上乗せ |
| 上記特例の要件を ともに満たす事業者 | 200万円上乗せ |
いずれの枠も補助率は原則2/3(通常枠と同じ)ですが、「賃金引上げ枠」に該当しかつ直近期または直近年度が赤字の事業者の場合は、補助率が3/4に引き上げられます。
※この特例に該当することで自己負担が1/4に減り、より手厚い補助が受けられます。
2024年に引き続き、2025年度でもインボイス特例という措置もあります。
これは、消費税の適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)への転換に対応する小規模事業者を支援するものです。具体的には、2023年10月のインボイス制度導入前は免税事業者だったがインボイス発行事業者の登録を行った事業者など一定の条件を満たす場合、補助上限額が一律で50万円加算されます。
対象経費:どんな費用が補助の対象になるの?
補助金でサポートされる経費(補助対象経費)は、「策定した経営計画に基づいて実施する取り組み」に直接必要な経費に限られます。具体的には、公募要領で以下の8つの費目が補助対象経費として挙げられています。
| 費目 | 内容 |
|---|---|
| ① 機械装置等費 | 事業に必要な機械装置や設備の購入費用(例:生産性向上のための新設備導入費用) |
| ② 広報費 | チラシ作成や新聞・雑誌広告、Web広告等の広告宣伝にかかる費用(例:DM発送費、SNS広告出稿費) |
| ③ ウェブサイト関連費 | ホームページやECサイトの制作・改修費用、SEO対策費用など |
| ④ 展示会等出展費 | 商談会や展示会への出展にかかる費用(オンライン展示会の参加費等も含む) |
| ⑤ 旅費 | 販路開拓や商談のための出張費用(交通費・宿泊費等) |
| ⑥ 新商品開発費 | 新商品の試作開発や市場調査等に要する費用(例:試作品の材料費、テストマーケティング費用) |
| ⑦ 借料 | 補助事業のために必要な機器や施設を借りるための費用(例:期間中のみ利用する機材レンタル料、イベント会場のレンタル費用) |
| ⑧ 委託・外注費 | 事業計画の実行にあたり専門家や外部業者へ依頼する費用(例:デザイン制作やシステム開発の外注費、広告運用代行費用) |
以上のような経費であれば、計画に沿った必要経費として補助対象にすることができます。広告宣伝費や設備投資費用、外注費用など、販路拡大や生産性向上に直結するコストを幅広くカバーできるのが持続化補助金の魅力です。
なお、注意点として日常の営業活動に伴う通常経費や、単なる老朽設備の更新費などは対象になりません。あくまで「新たな取り組み」に必要な経費が対象です。また、補助対象経費であっても経営計画に盛り込んでいない支出は補助の対象外となります。
計画外の支出や目的にそぐわない経費は認められませんので、「この費用は計画のどの部分に必要か?」を意識して計画書を作成することが大切です。
申請要件
対象事業者:どんな事業者が対象?
まず、本補助金を申請できるのは日本国内の小規模事業者です。小規模事業者とは業種ごとに定義された従業員数の範囲内の事業者のことで、例えば商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)は従業員5人以下、宿泊業・娯楽業や製造業などは20人以下といった規模の会社や個人事業主が該当します。
| 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 常時使用する従業員の数 5人以下 |
| サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
| 製造業その他 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
※業種の判定については、現に行っている事業の業態、または今後予定している業態によって、業種を判定します。業種の判定及び「常時使用する従業員」の考え方については、後日公開する別紙「参考資料」をご参照ください。
法人・個人は問いませんし、商工会や商工会議所の会員でなくても申請可能です。(商工会議所エリアの事業者は商工会議所経由で申請)
ただし大企業の子会社的な存在は対象外です。具体的には、資本金5億円以上の企業に完全子会社とされているような場合や、直近3年の平均課税所得が15億円を超えるような高収益企業は補助対象になりません。
要するに、「独立した小規模企業」であることが条件になります。また申請時点で開業していない(これから創業予定の)場合は一般型(通常枠)の補助対象になりません。すでに事業を始めていることが必要です(※創業まもない方向けには別途「創業型」の枠があります)。 さらに、本補助金に応募するためには経営計画を策定し、商工会または商工会議所にその計画の事前確認(事業支援計画書の発行)を依頼することが求められます。
このように地域の商工団体と連携して進める仕組みになっており、申請にあたっては事前準備と確認が必要となります。
全体の流れと申請期限
申請→入金まで半年~1年以上かかることが多いので、資金繰り等注意が必要です。
また、交付決定より前に発注等を行ってしまうと補助金の受給ができなくなることも要注意です。
- ~2025/6/3商工会・商工会議所へ事業支援計画書(様式4)の発行依頼事業計画を作成し、商工会・商工会議所に面談の予約。
事業計画のアドバイスを貰いつつ、支援計画書を貰う。 - ~2025/6/13電子申請JGrantsより、事業計画を提出して申請。
GbizIDプライムが必要になるので事前に作成しておきましょう。 - 2か月後くらい採択審査の結果、採択が決定されると補助金事務局から「採択通知書」が送付されます。
- 採択後見積書等の提出入手価格の妥当性を証明できる見積書等を提出します。
100万円を超える経費は相見積が必要なので注意。 - 交付決定審査の結果、補助金事務局から「交付決定通知書」が送付されます。
交付決定通知書に記載の交付決定日から補助事業を開始できます。 - 交付決定後事業実施発注・納品・支払は、交付決定後から可能です。
交付決定前に発注等してしまうと補助金の対象外になってしまうので注意。 - 事業完了実績報告発注書・納品書・請求書・支払の証拠・納品物の写真などを添付し、実績報告を行います。
どんな書類が必要になるかは、事業実施前に確認しておきましょう。 - 2・3か月後補助金額の確定実績報告に不備がなければ確定の通知がきます。
不備があったら修正して再提出します。 - 1か月後補助金の請求→交付振込口座等指定して補助金の請求をします。
請求後1か月後くらいに入金されます。 - 1年後事業効果報告書の提出補助事業の終了後から1年後の状況について、報告書を提出します。
なお、第17回の公募に間に合わなくても、おそらく年度内3回程度募集があると予想されます。
申請のポイント:採択されるためのコツと注意点
補助金の申請は競争です。せっかく手間をかけて申請するからには「採択されやすい」申請書を目指したいですよね。ここでは、持続化補助金の採択率を上げるためのポイントや、申請時の注意点をまとめます。
- 経営計画は具体的かつ戦略的に!
申請時に提出する経営計画書(補助事業計画書)は、審査において非常に重要です。自社の現状分析をしっかり行い、自社の強み・弱みを踏まえたうえでターゲットとする市場や顧客ニーズを的確に捉えた計画になっているかをチェックされます。
また、補助事業で行う取り組み内容(計画している販路開拓等)が具体的で実現可能性が高いことも評価のポイントです。「なんとなく売上アップしたい」ではなく、「○○市場向けに新商品を開発し、▲▲な手法でPRすることで半年後に売上○%増を目指す」等、数字や方法を明確に示すようにしましょう。審査委員は提出資料のみで判断するため、計画の背景や狙い、期待効果を第三者にも分かるよう丁寧に書くのがコツです。 - 必要書類の不備に注意!
申請にあたって提出すべき書類は公募要領にリストアップされています。例えば、電子申請システムへの入力項目のほか、先述の事業支援計画書(商工会・商工会議所が発行するもの)や売上高や従業員数等を示す書類など、決められた書類をすべて揃える必要があります。不備や漏れがあると審査以前に失格(書類審査でアウト)となってしまうので要注意です。
提出前にチェックリストを作成するなどして、書類の漏れ・記入モレがないか確認しましょう。特に電子申請になってから添付忘れや入力ミスが起こりやすいので、焦らず余裕をもって準備を進めることが大切です。 - 電子申請の準備は早めに!
持続化補助金の申請はJグランツ(電子申請システム)でのオンライン申請のみ受け付けとなっています。郵送や持参での申請はできません。そのため、電子申請に必要なGビズIDプライム(もしくはメンバー)アカウントを事前に取得しておきましょう。このアカウント取得には数週間程度かかることがあるため、「申請期限ギリギリに申し込んだら間に合わなかった!」ということにならないよう早めに手続きをしてください。暫定版のGビズIDプライムは本申請に使用できませんのでご注意ください。一度取得すれば他の補助金申請にも使えるので、まだお持ちでない方は早めに準備を進めましょう。 - 商工会・商工会議所と連携しよう!
持続化補助金は地域の商工会や商工会議所と二人三脚で進める補助金です。申請前には経営計画書の内容について地元の商工会議所等に相談し、事業支援計画書(様式4)の発行を依頼するプロセスがあります。プロの経営指導員からアドバイスを受けられる良い機会でもありますので、遠慮せず相談することをおすすめします。計画書のブラッシュアップだけでなく、提出書類の過不足チェックもしてもらえるので、結果的に申請の精度と採択率アップにつながるでしょう。依頼から発行まで時間がかかる場合もありますので、締切間際ではなく余裕をもって相談・依頼するようにしてください。 - 加点措置も活用!
持続化補助金には、満たすと審査で加点(プラス評価)してもらえる項目も用意されています。例えば、「経営力向上計画」の認定を受けている場合や、事業承継診断を商工会議所等で受けている場合などは提出書類を揃えることで評価時に加点されます。また、賃上げ(賃金引上げ)に取り組む事業者はそれ自体が加点対象になっています。該当しそうな項目があれば、公募要領の指示に従って必要書類を用意し、「○○の加点を希望する」旨を申請時にしっかり伝えましょう。ただし無理に狙う必要はありませんので、自社が活用できるものだけでOKです。
最後になりますが、期限厳守と計画遂行の意欲も大切です。申請期限(受付締切日時)は必ず守り、時間に余裕を持って送信を完了しましょう(電子申請は締切日の17:00がデッドラインです)。そして作成した計画は、採択されたかどうかに関わらず自社の成長プランとしてぜひ活かしていくくらいの気持ちで臨んでください。補助金はあくまで手段ではありますが、上手に活用すれば小規模事業者にとって心強い追い風になるはずです。
以上、2025年版の小規模事業者持続化補助金の概要をまとめてみました。
少しでも皆さんの資金繰りや販路拡大のお役に立てれば幸いです。
あなたのチャレンジを応援していますので、この補助金もうまく活用して事業をグッと前進させてくださいね! 😊